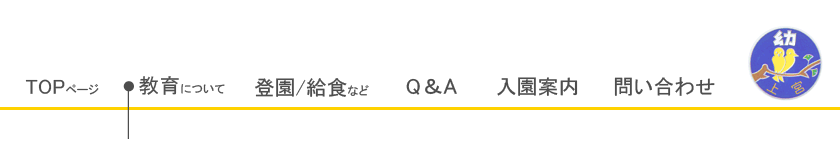
園 長 ご 挨 拶 学校法人上宮学園 赤ちゃんは、お母さんの目をじっと見つめながらオッパイを飲みますが、時々飲むのを休みます。「どうしたの?」と声を掛けてみたり、揺らしてみたりすると、再び飲みはじめます。どうして人間の赤ちゃんは飲むのを休んだりするのかと言うと、「どうしたの?」とお母さんに反応してもらいたいからだと言われております。他の動物はこんなことはしません。人間の赤ちゃんはお母さんに応答してもらいたいから休むのです。これはお母さんとのやり取りを楽しむ『会話の原型』と言われます。赤ちゃんは最初から“社会性”をもっているのです。
|
||
  |
情緒の安定を大切に考える 子供たちのための「ふつう」の場所 大人の社会が驚くほどのスピードで変化していたとしても、園の中で子供たち同士が作る社会は、今も昔も大きくは変わっていないように思います。
遊びの中からの幼児教育 目をかけ、声をかける 子供たちは周囲の人とのやり取りや遊びの中から日々様々な事を学んでいます。
園長先生による口演童話(月1~2回) 童話は心のミルクです 園長先生の童話に、子供たちは釘付けです。その表情は、ある時はビックリし目をまん丸に、可笑しい時は背をのけぞらして大声で笑います。その生き生きとした表情は、本当に童話の世界に入っているかのようです。おじいちゃん、おばあちゃんから、昔話を聞いた時代は、はるか昔の事となりました。ですから、これからも口演童話は、続けて行きたいと思います。 |
|
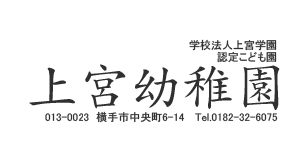
© 2016 Jyougu youchien